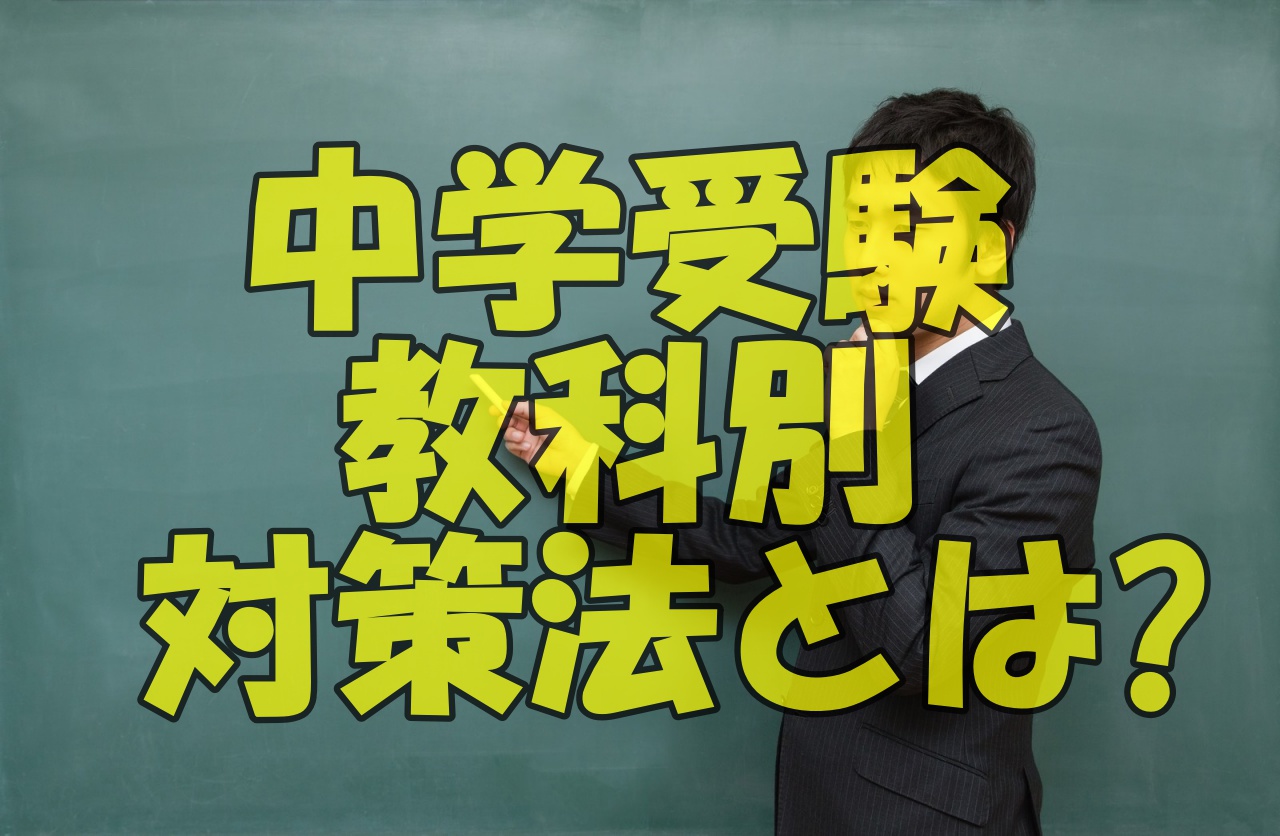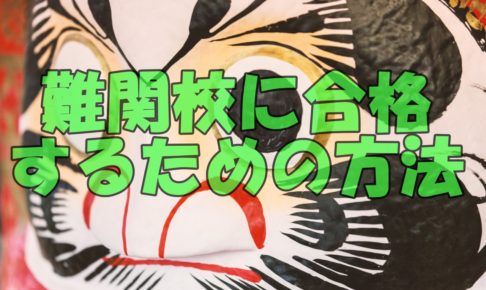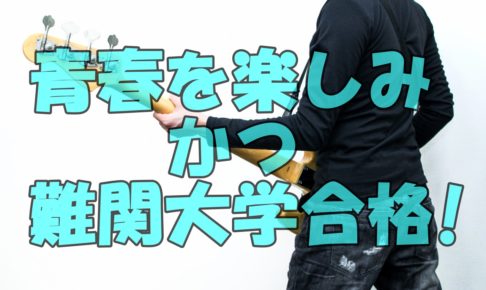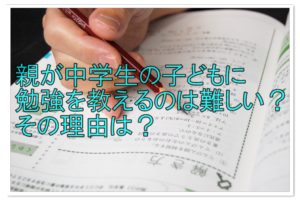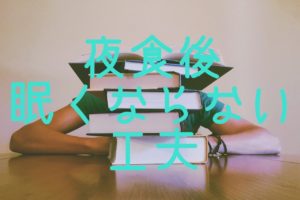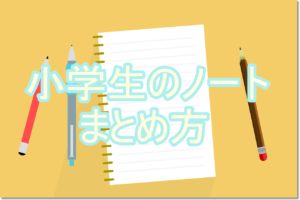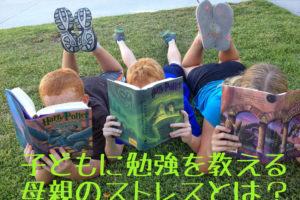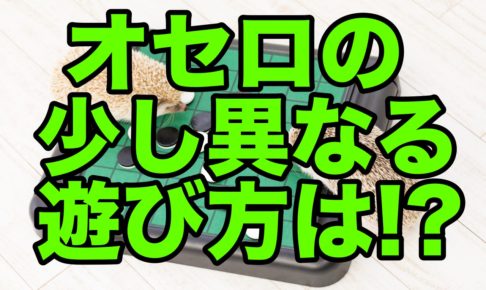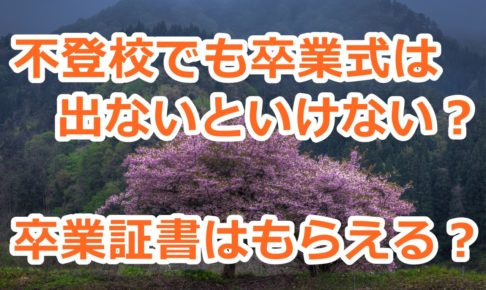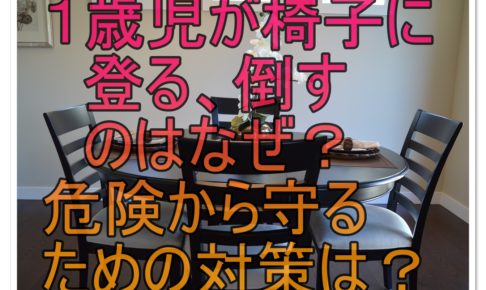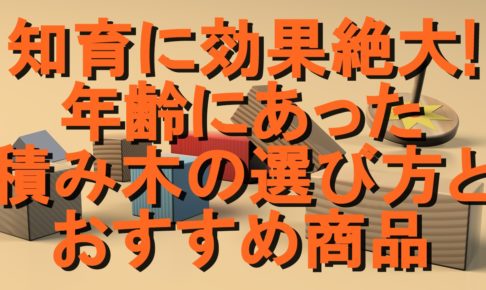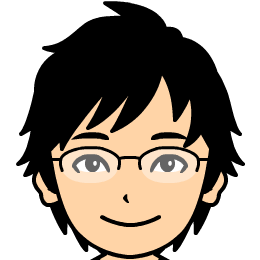
私立中学への進学を目指して塾に通っているけど、なかなか思ったように成績が上がらない。
そんな悩みを抱えている家庭が多々あります。でも、どこの家庭でも同じ悩みに頭をかかえているのです。
「なんでうちの子だけ。」という考えに陥りがちですが、その孤独感こそが受験の大敵です。
今回は、中学受験の勉強方法について教科別にご紹介しましょう。
目次
国語
国語はすべての基本
最近はよく目にするフレーズですので、皆さんも一度は見たこと、聞いたことがあるでしょう。
当たり前ですが、全ての教科のテキストもテスト問題も日本語で書かれています。
日本語が正しく読めなければ、算数・理科・社会の学習に支障が出るのは当然のことです。
実際に読解力が向上すると、国語の成績より先に他の教科の成績が上がるのですが、この話を保護者の方にすると、読解力はあがるものなのかと聞かれることがあります。
読解力は上がるもの
今でも時々、国語の苦手な子を持つ保護者の方が、
「読解力なんてあがりません。漢字や知識問題で点数をとりましょう。」
と塾の先生に言われたという話を耳にします。
たしかに、他の教科や漢字・知識などと比べると、上がるスピードはけっして速くはありません。
しかし、考えてみてください。
たとえば、小学校1年生のときには読めなかった新聞や本が、大人になった今では普通に読めていませんか。
これは大人になったから読めるようになったわけではなく、すこしずつ読解力がついていった結果、いつのまにか読めるようになったのです。
読解力に必要なもの
では、大人になった皆さんは、なぜ新聞が読めるようになったのでしょうか。
どんな力を身につけたのでしょうか。それをお子さんが身につければ、読解力はあがります。
語彙力・漢字力をつけましょう
やはり、ぱっと思い浮かぶのは、「知っている言葉の数が違う」ことでしょう。
また、漢字が読めること、その意味が分かることも重要です。
まず、漢字の数を増やすには、漢字ドリルなどの補助教材の活用が有効です。
このとき、漢字の意味や成り立ち、書き順も一緒に覚えるようにしましょう。
語彙を増やすには「目上の人との会話」をすることが大切です。
なにも勉強の話をする必要はありません。
遊びの話、趣味の話、なんでもいいのです。
子ども達がしらない言葉に触れる機会を増やすことが目的ですから。
ここで肝心なのは、大人の側で「簡単な言葉を使わない」ことです。
あえて難しい言葉を用いることで、話の流れから言葉の意味を理解する習慣を身につけることも必要だからです。
また、子どもの方から知らない言葉の意味が聞けるようになったら、その会話は大成功といえるでしょう。
音読・黙読をしましょう
脳はことばを区切ったところで言語処理をします。
ですので、文字を覚えたての子どもが、1文字ずつ区切りながら読んでいても、意味をなかなかとれません。
また、文章をめちゃくちゃな場所で区切りながら読んでも、意味が分からなくなります。
実は、文の読み方ができていない子どもが案外多いのです。
ですから、まずは音読をさせてみましょう。
このとき、「声を出しているところより、目が見ている場所が少し先」に進むようにすると、上手に読めるようになります。
「しっかり読む」≠「ゆっくり読む」
子どもの読書スピードが速いと、「もっとちゃんと読みなさい」と注意する方がいますが、これはNGです。
もちろん、読書慣れしていない人は(子どもに限らず)、速く読むと頭に入っていきません。
しかし、読書になれると次第に読む速さは上がっていくのです。
ゆっくり読むと最初の方が抜けていって、文章の全体像がつかめなくなることもあります。
小学6年生でしたら、最低800字/分くらいの速さで読めるように、訓練しましょう。
実は、これくらいの速さで読んだ方が集中力も上がり、しっかり読みとれるようになります。
そして、読み終わったら文章の内容を口頭で説明させるようにすると、読解力はどんどん上がっていきます。
もちろん、最初は全然説明できませんので、気長にやることが大切です。
時間を気にする
問題に集中しすぎると、1問に時間をかけすぎて、気づいたときには残り時間が無くなっていることがあります。
日頃から、1問あたり1分で解くことを意識しましょう(長い記述問題は、書き始めまでに1分くらい)。
算数
算数のポイントは「はやく」「正確に」
文章題の文章を読んで、式や図を書いて、計算して答えを求める。
これでどれくらいの時間がかかるでしょうか。
50分のテスト時間で25問出題された場合、1問あたりにかけられる時間は平均2分しか有りません。
じっくり考えていたら、あっという間に時間切れになってしまいそうです。
実際は、計算問題をはじめとした、1問を解くのに1分もかからない問題などがありますので、文章題にかけられる時間はもう少し多くなるでしょう。
しかし、計算速度が遅いと、本来なら時間を短縮するチャンスが、逆に足を引っ張ることにもなりかねません。
よく出る問題は、パターン化・公式化して、時間短縮できるように反復練習をしておきましょう。
勉強前の計算ドリル
家庭学習の最初に、計算ドリルをしましょう。
このときの注意は「簡単なもの」を「時間を計って」やること、答え合わせをして常に「全問正解を目指す」ことです。
おまけで、勉強前に計算ドリルをやることで脳の回転が速くなり、勉強の効率が上がります。
時間を計って取り組む
文章題を解くときは、最初は1問4分くらいで計算して、制限時間を決めて取り組むようにしましょう。
常に時間を意識する習慣づけはとても大切です。
そして最終的には1問2分で解けるようにしていきましょう。
また、国語でも書きましたように、時間を意識するようになると読むときの集中力も上がります。
社会
興味を持って取り組もう
「ぼくは記憶力が無いから。」
という子どもでも、大好きなトレーディングカードや人気アニメのキャラクターだったら、すぐに覚えられるというのは良く聞く話です。
要は、その教科が好きかどうか、自信があるかないかが記憶力を左右しているのです。
知ることを楽しいと感じる生活環境
先ほど、学習することは本能的に楽しいと書きましたが、日常生活の中で、学習することを否定されている子どもは、次第に学習することはつまらないこと、悪いことだと、無意識の中にすり込まれていきます。
そういう子どもは、社会や理科、国語の漢字や知識、算数の公式を覚えることが苦痛になってきます。
遊びの中で学ぶことができると、プラスの感情で学習ができるようになります。
地理なら旅行先がどんな場所なのかを、移動中に車や電車の中で話すなどが効果的です。
用語を覚えるだけではだめ
子ども達の社会のテキストを覗くと、大切な用語にマーカーで色が塗られていることがありますが、用語だけを覚えても意味はありません。用語を説明できるようにさせましょう。
テストの解答や選択肢を口頭でもよいので、説明できるかチェックしてあげてください。
できなかったものは、テストの設問や解説・テキストなどの文章を書き写し、それを音読して、その場で暗唱できるように習慣づけておくとよいです。
理科
普段から自然科学分野に興味のある子供は何も言わなくても理科は得意になっています。
そういう子どもは、細かな失点を防ぐために「きちんと覚える」ことを指導するだけでも十分です。
算数型と社会型の学習方法
生物分野のほとんどや、そのほかの知識部分については、社会と同様の学習方法で、対策できます。
物理分野をはじめとする計算などが必要な場面では、算数同様に解き方や公式を身につけているかが大切です。
ノートに何度も書くなどをして、しっかり覚えさせることが大切です。
算数は「どの公式を使えば解けるか」がわからなければ解けません。
読解力を身につけるか、パターン化するほどに反復練習をする必要があります。
ところが、理科はどの分野かはっきりしているので、どの公式を使うのかで悩むことはありません。
まとめ
・国語は全ての科目の基本であるが成績が上がるまでに時間がかかる
・国語の場合、まず語彙力、漢字力を身につけさせてから文章を読む力を身に着けていく
・算数の場合は、早く、正確にすることが大事なため、時間を決めて取り組む
・社会は興味をもつかどうかで決まる。興味を持たせるとともに重要な用語の背景を説明できるようにする
・理科は知識分野は社会と同様のやり方、計算分野は算数と同じやり方で対応可能
受験は合計点で決まります。得意科目があるのはよいのですが、得意科目だけ勉強することのないようにしましょう。
1科目くらい「どうしても苦手だ」という科目があっても、他の科目でカバーするという方法ができます。
しかし、「僕は算数が得意だ」というのは、「ほかの3科目は苦手だ」ということの裏返しになってしまいますね。
得意な1科目だけで、苦手な3科目をカバーするのは大変です。
日頃から計画を立ててバランスよく勉強を進めていくようにしましょう。
お子様が小学校6年生で成績が書かれないくらいに成績が悪い、けど、中学受験で地区の難関校や中高一貫校に行かせたい・・・
そう考えている保護者の方もいらっしゃると思います。
そう言う方は、この記事をご覧ください。
高校受験合格の話ですが、お子様が小学校6年生でしたら、中学受験でも十分対応可能です。
さらに、少し早いと思いますが、大学受験もこの時点で計画立てている方はこちらの記事も参考になりますよ。