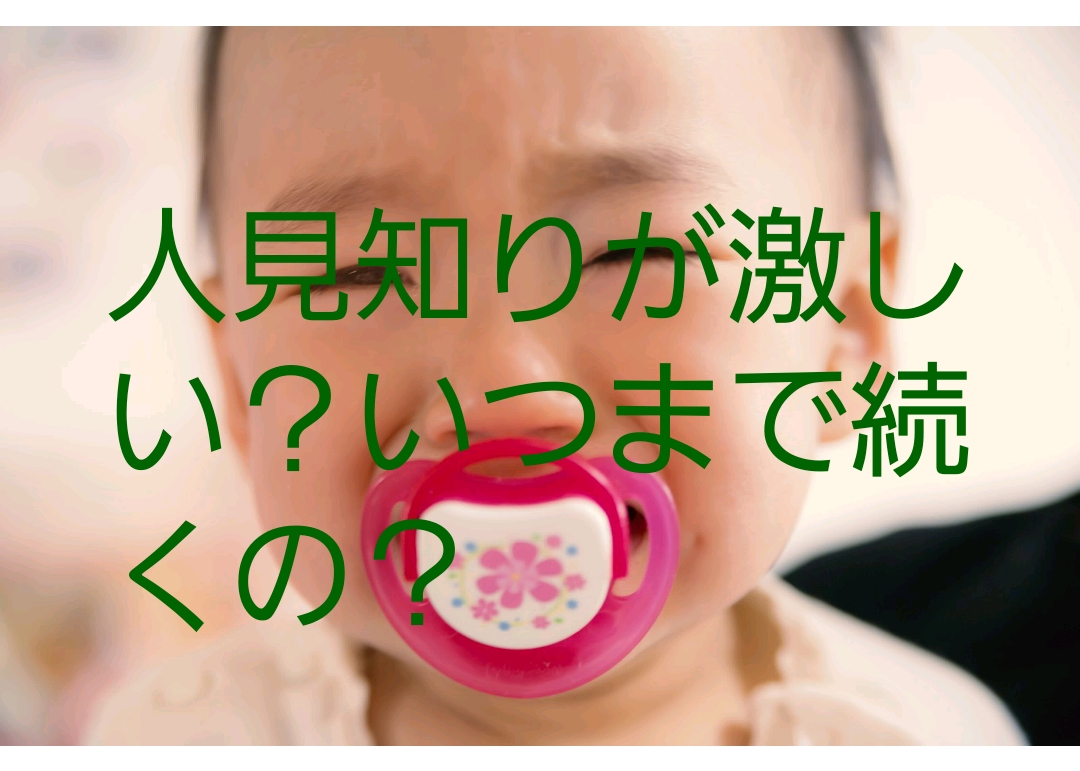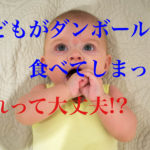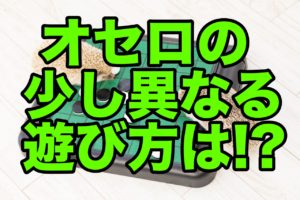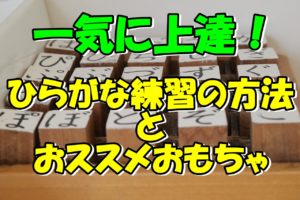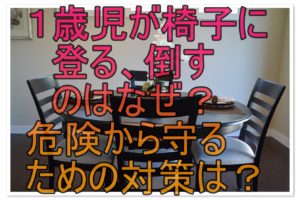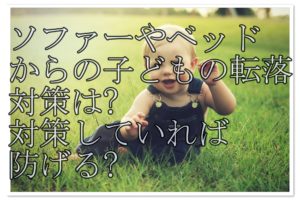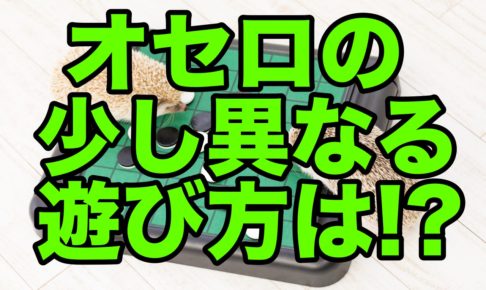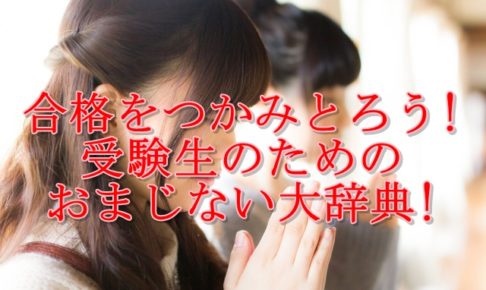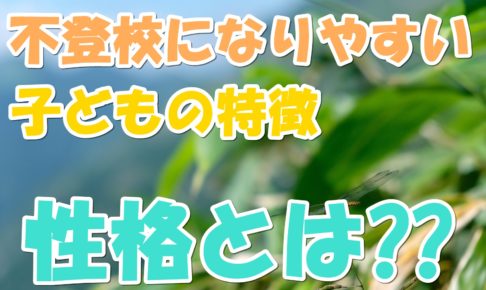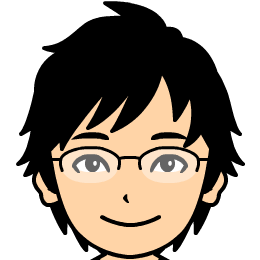
子育ての仕方について色々な悩みを持たれていませんか?
「子どもが泣き止まない、どうすればいいのだろう、、、」
「子育てでイライラした場合先輩ママはどうやって解決したのだろう・・」
「待機児童になった場合どうすればいいのだろう・・・」
と、子どもが小学校へ上がるまででもたくさんの悩みが発生します。
そう行った悩みを投稿して、回答してもらうコミュニティの場として、「ママリ」があります。
小学校入るまでの子どもに対しての相談内容がかなり多く、それに対しての回答もかなり掲載されております。
「どうすればいいのだろう・・・」
と一人で悩む前に、一度ママリで調べてみてはいかがでしょうか?
生後6ヶ月を過ぎると、お母さんや他の人との見分けがつくようになり、人見知りが始まりますね。
近所の人や、おじいちゃん、おばあちゃんから「こんにちは」と話しかけられたとたん火がつくように泣き出す子ども。
お母さんとしては困りますよね。
声をかけた方も、しまった!といった顔になってしまい、お互い気まずくなる。
なんていう経験をされた方も多いと思います。
私の所も自身の母親(子どもにとってはおばあちゃん)が話しかけたらずっと泣いてます。
そしておじいちゃんの所へは近寄りもしないです。
顔を見た途端にこの世の終わりかのように大泣きします。
それに比べ、お友達の子は、誰に声かけられてもニッコリしてて羨ましい。
愛想がいいほうが皆に可愛がられるのに。
そう思ったことはありませんか?
ではなぜ人見知りをするのか。
しない子との違いはなんでしょうか。
人見知りって何?
人見知りのメカニズム
まず、生後~6ヶ月までの赤ちゃんは、 目がぼんやりとしか見えていません。
新生児で0.01~0.02。
3ヶ月で大体0.03~0.05、6ヶ月位で0.1程と言われています。
ぼんやりとしか、見えていない状態から徐々に、今目の前にいるのが誰か?を、認識していく中で、親と他人。
またはよく見る人かそうでないかを覚えていくのです。
6ヶ月くらいになると外からの音や映像で「こわい」や「きらい」の感情が芽生えます。
生まれてすぐのモロー反射は、大きな音や光など条件反射で起きますが、それにプラスして感情を表す。
見たことない→怖い=人見知りになるのです。
人見知りがあると言うことは、親とそれ以外を区別できている。
人は皆味方ではないと言う人間の本能なのです。
至って当たり前のことなので、今困っているお母さんも心配ご無用です。
逆に「うちの子凄いわ」と誉めてくださいね。
また、人見知りには、色々なタイプがあります。
- 固まってしまう
- 目を反らす
- 凝視する
- ギャン泣き
どれも困りますよね。
中にはこれらの複合型もあり、外に連れ出すのも辛い。
と悩まれてなしでしょうか?
また終わりはいつか来るのか?
このまま保育園や幼稚園にいっても馴染めなかったらどうしよう。
人見知りが強いお子さんを持たれる方は、不安だと思います。
いくつまで続く?
一般的には、2~3才で落ち着くと言われています。
この頃になると、親が他の人と話している様子を見て「大丈夫なんだ」と判断できるんですね。
最初は、背中に隠れて様子を見ていた子どもも、だんだん興味をもって相手を見る様子が出てきたりします。
でも、そこで知らない人にいきなり話しかけられたら、固まったり泣き出したりします。
元の木阿弥になってしまいがちです。
最初はお母さんをクッションにして、相手の言葉を伝えてみましょう。
「こんにちはってご挨拶できるかな?」
「一緒に遊ぼうって誘ってるよ?お母さんと一緒にいってみる?」等々。
少しずつ外の輪の中に誘い出してみましょう。
慣れてくれば、親を介さず自分から話しかけたりできるようになってくるでしょう。
人見知りしない子って?
では、人見知りをしない子は親と他人の区別がついてないのでしょうか。
誰にでもニコニコ。
自分から他の人に走っていってしまう。
これはこれで親としては心配です。
他人と区別がついていないのでしょうか。
いいえ。やはり持って生まれた性格と言うのもあります。
また、育ってきた環境で周りに沢山の人がいる(親世代と同居)や、低月例からの保育園入所などでも変わってきます。
また、核家族の中で育っていても、誰にでもニコニコ人見知りをしない子もいます。
持って生まれた性格と環境で、同じ親から産まれて育てられても、人見知りと言うのは、現れ方が様々なのです。
兄弟でもこんなに違う
AちゃんとBちゃんの姉妹は、お父さんとお母さん、お祖母ちゃんの、5人暮らしです。
Aちゃんは、よく飲み、よく寝て俗に言う「手のかからない子」でした。
また、赤ちゃんの頃から目が合うとニッコリと、逢う人毎に笑いかける愛嬌の良い子と近所でも評判でした。
最初の子どもと言うこともあり、お母さんは仕事を辞め、2歳まで家庭保育でお祖母ちゃんと3人で過ごすことが、多かったのです。
この頃、Bちゃんが産まれました。
Bちゃんは、Aちゃんとは真逆で、お腹一杯でも泣き止まず、ずっとお母さんが抱っこしてないと、寝ない子でした。
Aちゃんは丁度イヤイヤ期真っ盛り。
いきなり現れた下の子に焼きもちを焼き、二人して大泣きの状態で、お母さんはへとへとでした。
さらに追い討ちをかけるように、お父さんが勤める会社の、不況もあり、お母さんはBちゃんが産まれて3ヶ月から、仕事に出ることになりました。
姉妹はAちゃんが2才9ヶ月。
Bちゃんが3ヶ月から同じ保育園に通い出しました。
Aちゃんは喜んで保育園に通います。
ところが、Bちゃんは、朝からお迎えにいくまでずっと泣いていたようです。
保育士の先生の
「すぐに慣れますよ。環境が変わって不安なのは、最初はどの子も同じですから」
と言う言葉を頼りに、半年ほど過ぎました。
Bちゃんは登園したときに、決まった先生だと、泣かずに「ばいばい」できるようになりました。
しかし、たまたま他の先生に、引き渡しをすると、アウト。
決まった先生がお休みの日は相変わらず夕方まで泣いていました。
それはなんと、3才まで続きました。
また、保育園に行きだした頃、お父さんも仕事が忙しく、子ども達が起きている時間に、帰宅できる日はあまりありません。
たまに早く帰れた日には、子ども達と遊ぶことをとても楽しみにしていました。
Aちゃんも、Bちゃんもお父さんと遊ぶのをとても楽しみにしていて、お父さんが早く帰れた日には、3人で大声で笑いながら、遊んでいました。
ある日お父さんが散髪へ。
行く時間が取れないからと、かなり短くカットして帰ってきました。
「ただいまー」と玄関に入ったお父さん。
出迎えたBちゃんを抱き上げようとした途端Bちゃんは大泣き!
なんと、髪を切ったお父さんを「他人」と認識してしまったのです。
大急ぎでお母さんに助けを求めるBちゃんと、呆然と玄関で固まるお父さん。
勿論お母さんや、お祖母ちゃんがカットしてもBちゃんは平気です。
髪を切ってもお父さんを「認識」出来るようになったのは2才になろうとする頃でした。
Bちゃんはとても感受性の高い子でした。
ちょっとした違いや、雰囲気を素早く察知し、捉えてしまう。
お母さんの姉妹がそのタイプだったようで、遺伝的な性格のようでした。
一方Aちゃんはお父さん譲りののんびりな性格でした。
親のせいではない
「育て方が悪い」と、親世代や祖父母世代から言われたことはないですか?
昔は「癇の虫」と、言われていたようです。
決して親のせいではないのです。
同じように育ててもAちゃん達姉妹のように、まるで正反対の反応を見せる子もいます。
初めにかいたように、他人と身近な人との区別がつくようになる、生後半年よりも前から、集団生活をしていたにも関わらず、長く人見知りをしたBちゃん。
他の人とあまり接せず、イヤイヤ期にいきなり集団生活が始まったAちゃんはすんなり溶け込みました。
二人ともお母さんとずっと過ごしたかった筈です。
これは、性格の現れです。
お父さんにすら、雰囲気が変わっただけで大泣きしていたBちゃんですが、3才を過ぎた頃は嘘のように、誰にでもニコニコ手を降るようになりました。
まとめ
- 人見知りは早くて生後6ヵ月以降始まる
- 人見知りしない子もいる
- 兄弟でもかなり違う
- 人見知りは親のせいではない
きっと他の人を受け入れず、お母さんから離れないお子さんに疲れている方も多いのではないでしょうか?
なぜうちの子だけ?と悩まないで下さい。
お子さんは「お母さんが大好き」なだけ。
遠くない未来に、離したくなくても勝手に繋いだ手を振りほどき、子どもは歩いていきます。
「何でこの子は他の人を見るだけでこんな反応をするんだろう」
と思わず
「もう~っ。そんなにお母さんが良いの?甘えん坊ね」
と、にっこりお子さんに向かって微笑んでみてください。
心が少し軽くなりますよ。
人見知りには必ず終わりが来ます。
焦らずゆっくりお子さんと過ごしていきましょうね。
子育ての仕方について色々な悩みを持たれていませんか?
「子どもが泣き止まない、どうすればいいのだろう、、、」
「子育てでイライラした場合先輩ママはどうやって解決したのだろう・・」
「待機児童になった場合どうすればいいのだろう・・・」
と、子どもが小学校へ上がるまででもたくさんの悩みが発生します。
そう行った悩みを投稿して、回答してもらうコミュニティの場として、「ママリ」があります。
小学校入るまでの子どもに対しての相談内容がかなり多く、それに対しての回答もかなり掲載されております。
「どうすればいいのだろう・・・」
と一人で悩む前に、一度ママリで調べてみてはいかがでしょうか?